-
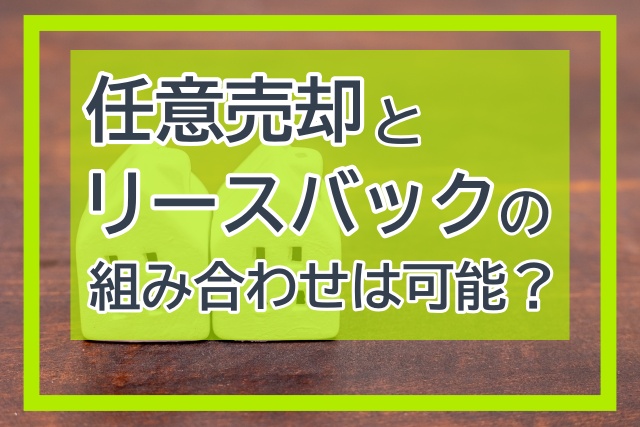
任意売却とリースバックの組み合わせは可能?
月々の住宅ローンの返済ができなくなった際に、家の売却をしようと思っても家の売却代金が住宅ローンの残債より低い場合、本来であれば不足分を一括で支払わなければ金融機関は抵当権の抹消に応じてくれません。 つまり家の売却はできないのです。 月々の返済はできず、売却しようと思っても売却もできないのでそのまま月々の返済が滞ってしまい、最終的には裁判所による競売で強制的に安く売られてしまいます。 競売になってしまう前に、金融機関と交渉をし、残債以下での売却の承諾を取り付けて競売を回避することが出来る「任意売却」。 ※「任意売却」についての詳細はこちらの記事を参照ください。 任意売却を選択することによって、競売は回避できますしその他あらゆる面でメリットが多くあるのですが、家を売却することになるので引越しが必要になります。 しかし今まで愛着を持って住み続けてきたご自宅。 お子様の学校の事情や様々な理由でできるならば引越しを避けたいと考える方は多いはずです。 ではここで、任意売却で売却することになった自宅にリースバックを利用してそのまま住み続けることは可能なのでしょうか。 ・そもそもリースバックとは? リースバックとは自宅を不動産業者や投資家に一度売却したうえで賃貸借契約を結び、家賃を支払いながら引き続き住み続けることができるというものです。 【リースバックの流れの図】 リースバックで業者や投資家が購入する際には、物件の市場価格の70~80%とやや低めの金額で購入することが一般的です。 仮に市場価格通りで購入するのならば、その分家賃の設定金額が非常に高額になってしまうこともあります。 ・任意売却とリースバックを組み合わせる? 任意売却をする場合、売却金額に関しての決定権は金融機関にあります。 いくら以上で売却しなければ任意売却には応じずに競売にする。 と判断されてしまうので、あくまでも金融機関側が指示してきた金額で販売しなければなりません。 当然、金融機関は少しでも多く回収したいので安く売ることに関しては同意してくれることがないのです。 一方でリースバックは前述の通り購入者である業者や投資家は市場価格より安くないとリスクを許容しきれないので市場価格で購入するケースはあまりないのです。 このように任意売却では市場価格で売却する必要があり、リースバックは市場価格より若干安く売却することになる為、任意売却とリースバックを組み合わせた場合売買代金の折り合いがつかず不成立となる可能性が高いのです。 もちろん、これは一概に言えるものではなく、中には金額の折り合いがうまく付き成立するケースもありますし、そもそも査定をしてみたら住宅ローンの残債より高く売却ができるケースもあります。 ・まとめ 住宅ローンの返済が困難になった場合、競売ではなく任意売却を選択する方がメリットは多く様々な負担が軽減されます。 さらにリースバックを利用してそのまま家賃を支払いながら住み続けられれば引越しが不要となり今まで通り住み続けることが出来るのです。 しかしそのためには金額が折り合うかどうかを慎重に見極める必要があると言えるでしょう。 当社では任意売却とリースバックのどちらも多くの実績があり、これらを組み合わせて成立させることができたケースもございます。 まずはご相談いただきましたらすぐに駆け付けます。 お気軽にご連絡お待ちしております。
ブログ
-
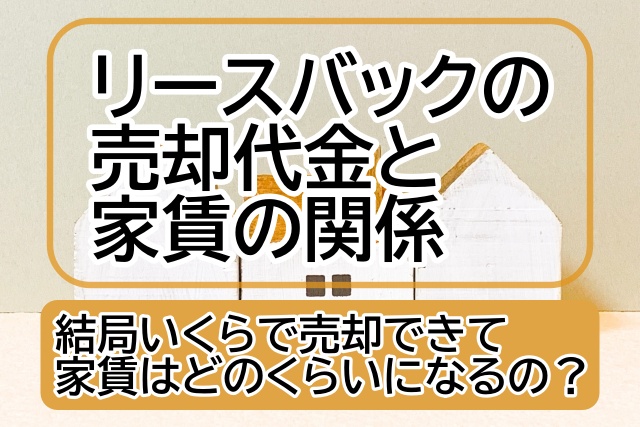
リースバックにおける売却金額と家賃の関係
自宅を不動産業者や投資家に一度売却したうえで賃貸借契約を結び、家賃を支払いながら引き続き住み続けることができるリースバック。 【リースバックの流れ】 自宅の売却代金を一括で受け取れ、その使用用途も問われないので様々なシーンでリースバックが活用されています。 ではこのリースバック、一体どのくらいの金額で売却できて、家賃はどのくらいになるのでしょうか。 今回はリースバックの売却金額と家賃について説明します。 売却価格の目安は? まずリースバックにおいて、自宅がいくらくらいで売却できるのかというと、大まかな目安として、自宅の市場価格の70~80%程となります。 リースバックで購入するのは不動産業者や投資家です。 そこに居住する目的で購入するのではなく、ビジネス・投資を目的として購入することになりますので、市場価格通りで購入すると、もしリースバックの利用者がすぐに退去してしまった場合、その家を売却する必要が出てきます。 家を購入する際は、家の売買代金の他に様々な諸費用が必要で100万円単位になることがあります。 購入代金+諸費用が売却代金を上回ってしまうと赤字になってしまうので、そうはならないように市場価格の70~80%という金額が設定されることが多くなります。 月々の家賃の目安は? 次にリースバックで住み続けるにあたって、月々の家賃はいくらくらいになるのかを説明します。 家賃はどのように決められるのかというと、家の売買代金を基準に決定します。 地域や物件の状況や築年数、戸建てかマンションか等によっても違いはありますが、大まかには家の売買代金の7~15%が年間の家賃となるので、それを12で割れば月々の家賃が算出できます。 この7~15%という数字を利回りと言います。 例:売買代金が1,500万円、利回りが8%の場合 1500万円 × 0.08 ÷ 12 = 10万円 この場合10万円が毎月の家賃となります。 リースバックにおける家賃はこのようにして決められます。 売却代金と家賃の関係 ここまで、リースバックにおける家の売買代金と家賃について説明しましたが、実はリースバックにおいてこの二つは最初から決まっているものではありません。 どういうことかと言うと、家の売買代金を安くすればその分家賃も抑えられますし、逆に家の売買代金を高くすれば家賃も高くなるのです。 例えば、市場価格が2,000万円の家があったとして、ここをリースバックするとなると、 市場価格の8割が1,600万円となり、利回りを8%と設定すると約10.6万円が月々の家賃となります。 1,600万円 × 0.08 ÷ 12 ≒ 10.6万円 ここで、市場価格は2,000万円ですが、売買代金1,200万円とした場合はどうなるかというと、買う側にしてみれば市場価格よりもずっと安く買えるのでその時点でリスクが非常に少なくなり投資として魅力的だと判断できます。 すると利回りの設定も例えばですが5%といった低い数値で設定できるようになります。 1,200万円 × 0.05 ÷ 12 = 5万円 このように売買代金を安くすることで、利回りも低く設定されるので月々の家賃を非常に安く抑えることが可能となるのです。 言い換えると、リースバックでは利用する方の要望に応じてある程度条件をオーダーメイドすることができると言えます。 最初に多く資金を確保したい場合は高く売却し、その分家賃は高くなる。 最初に確保する資金はそこまで多くなくていい場合は安めに売却し、家賃も低く抑えられる。 というように利用する方の状況に応じて使い分けられるのです。 リースバックで売却した家を買い戻す場合 リースバックでは一度売却した家を好きなタイミングで買い戻すことが可能です。 この時の買戻し金額は最初の段階で確定させておき、契約書に記載しておくことになるのですが、目安として売却代金の115~130%で設定されることがほとんどです。 ここで、買戻しを予定している方の場合、売却代金を高くしてしまうとその分買戻し金額も上がってしまい、なかなか買い戻し辛くなってしまいます。 買戻し金額が売却代金の120%で設定されるとして ①売却代金が1,800万円の場合 1,800万円 × 1.2 = 2,160万円 ②売却代金が1,200万円の場合 1,200万円 × 1.2 = 1,440万円 このように買い戻しを予定している場合は最初の売却代金を安くすることで、買戻しも非常にしやすくなるということを覚えておく必要があります。 まとめ リースバックにおける売買代金と家賃の関係について説明しました。 売買代金や家賃を算出する際の利回り、買戻し金額の設定などは不動産業者や投資家によっても大きく異なります。 家スクのリースバックでは当社だけではなくそのエリア毎で20社以上の数字を比較しお客様にとって最適なリースバックを実現させます。 家スクのリースバックの7つの特徴 特に大阪、和歌山、奈良、兵庫のリースバックは多くの実績もあります。 まずはお気軽にご相談ください。
ブログ
-
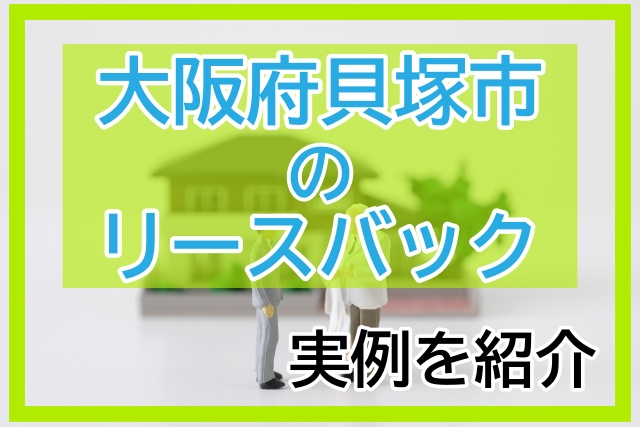
大阪府貝塚市のリースバック ~実例を紹介~
大阪府貝塚市の一戸建てにお住まいの70代のご夫婦からのご相談です。 最初の問い合わせは埼玉県大宮市にお住いの息子様からの相談で、両親の家のリースバックについて相談したいとお電話がありました。 リースバックについて大まかにお電話でお話し、後日、実際にご両親がお住まいのお家にてご両親と息子様もLINEのスピーカー通話にした状態で一緒にお話をしました。 お二人の収入源は年金と、ご主人様がたまに警備員のバイトをしているくらいとのことです。 奥様が数年前よりパーキンソン病を発症し、進行性のため年々震えが大きくなり歩行も困難になってきてしまい、当然車の運転等もできないため、ご主人様ができる限り付き添っている必要がありますが、そのご主人様も昨年体調を崩しこの先の不安が増したとのことです。 筆者の母親も晩年はパーキンソン病により日々動きづらくなる身体と戦っていたため、奥様のお話を聞いている時はどうしても感情移入してしまいました。 今後はいつ施設への入所等を検討することがあってもおかしくないため、今の内から可能な準備をしたいのと、手元に資金がないのは不安なのでリースバックを検討しているとのことでした。 息子様は東京でマンションを購入しており、大阪へ戻ってくる予定はないためそれなら実家は今のうちに現金化して少しでも両親のこれからが楽になれば良いとのお考えです。 お家は築38年の戸建てで土地は約70㎡、お家の前面道路が狭くその点でやや市場性に劣る物件と言えます。 当社に相談する前に他の業者にもリースバックの相談を持ち掛けたそうですが、そこの業者には上記の理由からリースバックを断られてしまったそうです。 相談後、当社での買取代金や家賃を提示するとともに、大阪府貝塚市でリースバックを扱う他の業者さんにも金額をご提示いただきました。 やはり物件の条件が厳しいため、買取不可の返事が多かったのですが、最終的に売買代金480万円、4.3万円/月の内容でリースバックを進めることとなり、無事に決済も完了しました。 4.3万円の家賃と月々の生活費は年金とご主人様のバイト代で賄っていけるので、480万円の資金は今後何かあった時の為に手を付けずに残しておくことができるので、いざというときの為にとても安心と喜んでおられました。 このように、自宅を売却し、そのまま賃貸借契約を結び家賃を支払い続けながら住み続けるリースバック。 手元に資金が必要だけれど、引越しもなかなかできないという方にとても有効な方法です。 家スクのリースバックは大阪府貝塚市をはじめ 岸和田市 ●熊取町 ●泉佐野市 ●泉南市 ●阪南市 ●岬町 ●和泉市 ●泉大津市 等の大阪府南部エリア、さらには大阪府全域で多くの実績があります。 ・家スクのリースバック、7つの特徴 ①住み慣れた家に、住み続けられる 引っ越しするとなると引っ越し資金の確保や、新しく住む家を探す手間があります。 引っ越しは時間もお金も労力もかかります。そんなわずらわしい引っ越し作業をリースバックなら行わずに売却することができます。 住み慣れた場所、住み慣れた家から離れなくて済むので、精神的な負担も少ないと言えます。 ②老後の資金調達にも 老後の介護費用や施設の入所費用などまとまった資金が必要な時に大いに有効です。 ③20社以上の金額を比較できる リースバックを依頼するにしても、どの業者に依頼すればいいか分からない方は多いはずです。少しでも高く売却し、少しでも月々の家賃は抑えるために家スクでは当社を含め20社以上の買取価格と家賃を比較しお客様の条件に一番合ったリースバックを提案します。 ④ローンが残っていても可能。まとまった資金の調達にも 当社のスキル・弁護士との連携により任意売却・債務整理と組み合わせ、リースバックを行っております。住宅ローンが残っていたり、その他借り入れがあり、まとまった資金が必要な場合も大いに活用できます。 ⑤将来的に買い戻すことができる 一度はリースバックで売却したお家を将来、ご自身や親族の方で買い戻すことが可能です。買い戻す際の金額等の条件も事前に決めておけるので、いつでも買い戻すことができ安心です。 ⑥相続が“争”続になる前に ご自身が亡くなった後、煩雑な相続手続きでお子様に負担をかけたくない。そもそも相続人がいないなど、相続に伴うトラブルも事前に現金化しておけば防ぐことができます。 ⑦物件売却を周囲の方々に知られない 周囲の人に突然の引っ越しの理由を説明しなくてはいけない場合がありました。体裁を考え、理由をお話ししたくない場合も。また、売却物件として不動産会社などのチラシやウェブサイトに載ってしまうと、どこから話が漏れるか分かりません。 リースバックを使えば、そういったこととは無縁です。 相談は無料です。 お気軽にお問合せ下さい。
ブログ
-

リースバックで後悔しないために!7つの後悔事例を紹介
自宅を売却し、そのまま賃貸借契約を結び家賃を支払い続けながら住み続けるリースバック。 まとまった資金が調達できるので ・老後の生活資金 ・施設や病院への入所費用 ・借入の返済 ・事業資金の調達 などといった目的で近年、利用される方はますます増えています。 しかし、よく検討しないままリースバックの契約を進めてしまい、後になって後悔するというケースも見かけられます。 契約の際も、実際に賃貸として住み始めてからも安心してリースバックを利用できるよう、今回はよくある後悔事例を紹介します。 リースバックを検討している方はぜひこの記事を参考にしていただければと思います。 1.定期借家契約のため、短期間で退去が必要になった リースバックでは、自宅の売買契約と同時に賃貸借契約を締結することになります。 ここで注意していただきたいのが賃貸の契約が「定期借家契約」の場合、契約期間があらかじめ決められており(2~3年の場合が多いです)、契約の更新がないため、契約期間が満了すると同時に借主は退去をするか買戻しをする必要があります。 貸主と借主の双方の合意があれば契約期間満了後に再契約をすることも可能ではありますが、リースバックで最初に契約する際には注意しておく必要があります。 2.家賃が高く支払いができなくなってしまった リースバックを利用する方の中には、急いで資金を調達する必要がある状況の方も多く、そういった方の場合、とにかく目先の資金の確保ばかりに重点を置いてしまい、月々の家賃の金額について深く考えないこともあり得ます。 せっかくリースバックで住み続けることが目的だったのに、家賃が支払えず退去するとなると本末転倒です。 月々の家賃の金額が無理なく支払えるかどうかを注意深く検討してからリースバックを進める必要があります。 3.相続で揉めてしまった リースバックは自宅の所有権が当然に買主に移ります。 子供等の親族に何も相談せずに進めてしまうと、将来ご自身が亡くなった時に家の相続を期待していた親族と揉める可能性があります。 自宅の相続についてある程度事前に相談しておく方がトラブル回避になります。 4.リースバックを当てにしていたが、利用できなかった 住宅ローンの返済が厳しくなったので、リースバックをしようと考えている方もおられると思います。 リースバックは基本的には住宅ローンの残債以上で売却する必要がある為、住宅ローンの残債が多く残っている場合は買取り代金が残債に届かないということになり、リースバックが利用できません。 住宅ローンを借入している金融機関と交渉をし、住宅ローンの残債以下で売却する「任意売却」と併せて進めるということも可能ではありますが、「任意売却」では自宅を相場通りの金額で売らなければ金融機関が任意売却に応じてくれません。 一方、リースバックでは売買代金はおおよそ相場の7~8割となることが多く、売買代金の折り合いがつかずにリースバックが利用できなくなるということもあります。 リースバックは必ず可能ではないということを理解しておく必要があります。 5.修繕費用や明渡し時の現状回復費用で揉めた リースバックでは賃貸の契約を結んで住み続けることになります。 家の修繕が発生した際に、どちらがその修繕を行うのかということを事前に取り決めておく必要があります。 実際に修繕が発生したタイミングで、大家に対応をしてもらえなくて慌てるといったことがないようにしておきましょう。 リースバックの場合、台風などで火災保険が利用できる範囲以外の修繕は賃借人の負担とするという条件の場合も多くあります。 同じように退去時の現状回復条件も事前に確認しておく必要もあります。 6.買戻し金額が高くて買い戻せなかった リースバックでは一度売却して家賃を支払いながら住み続けている自宅を、再度買い戻すことができるというのも非常に大きなメリットだと言えます。 しかし買戻し金額についてあらかじめ決めておかなければ、いざ買い戻したいというタイミングで非常に高額な売買代金を提示されてしまうと、買戻しができなくなってしまいます。 リースバックの契約を進める最初の段階で、将来の買戻し金額についても取り決めておく必要があります。 7.家を転売されてしまった 当初契約していた会社が家を転売してしまう可能性があります。 ただ、ご安心いただきたいのは、転売されても賃貸の条件は引き継がれるので急に退去を迫られたり家賃が上げられたりするということはありません。 しかし、突然転売され所有者が変わるというのは不安なものです。 事前に転売の可能性等を確認しておく必要があります。 以上がリースバックにおいてよくある後悔の事例です。 利用しやすく非常にメリットの多いリースバックですが、これらの点を見落としてしまうと思わぬ後悔に繋がります。 家スクでは大阪・和歌山・奈良・兵庫を中心にリースバックの相談を受け付けています。 もちろん上記の内容も事前にきっちりと説明します。 お客様の要望に一番沿った内容のリースバックを実現いたしますのでぜひお気軽にご相談ください。
ブログ
-
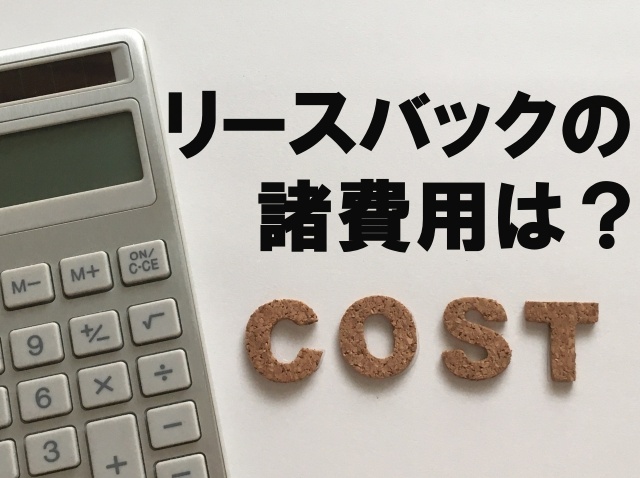
リースバックにかかる諸費用は?
家を売却して、その後売却した家に家賃を払って住み続けるリースバック。 昨今はかなり浸透してきており、当社にも多くの相談が寄せられます。 リースバックの大まかな流れはこちらの図のようになります。 では今回は、お客様がリースバックをする際にかかる諸費用にはどういったものがあるのかを解説していきます。 リースバックにかかる諸費用 ①不動産仲介手数料 リースバックをするためには家の売却が伴います。 業者等が直接買い取る場合は必要ありませんが、仲介業者が間に入る場合は不動産仲介手数料が必要となります。 不動産仲介手数料は、宅建業法(宅地建物取引業法)という法律で上限額が定められています。 仲介手数料の上限額は、物件価格によって異なります。 ・不動産の売買額が400万円を超えた場合 物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税 ・不動産の売買額が0~400万円以下の場合 33万円(税込) この金額を上限として仲介手数料が発生します。 ②登記費用(司法書士費用) こちらも家の売却時に発生する費用です。 家に抵当権が付いている場合はその抵当権の登記を抹消する費用、登記されている住所と今のお客様の住民票の住所が異なる場合は住所変更の登記費用等がかかります。 金額としては抵当権の数や住所変更の有無によって変わりますが、大まかに1万円~5万円程度のケースが多いです。 別途相続登記等が必要な場合はさらに十数万円程度かかります。 ③印紙代 こちらも売却時に発生する費用の一つで、家を売却する際に交わす不動産売買契約の売買契約書に収入印紙を貼付し、印紙税を収める必要がございます。 印紙代は表の通りの金額です。 ④保証委託料 リースバックをする際に、家の売買契約と同時に賃貸借契約を結びます。 賃貸借契約を結ぶ際には家賃保証会社への加入が必須条件となっているケースがほとんどで、この保証会社へ支払う保証委託料が必要となります。 金額の目安としては、保証会社によってもまちまちですが、取り決めた1か月の家賃の50~100%の金額が必要となります。 ⑤敷金・保証金 リースバックで今後、大家となる業者や投資家によっては敷金や保証金として家賃の1~2か月分が必要となることがあります。 こちらに関しては、家賃の未払い等が無ければ将来退去する際やリースバックした家をお客様が買い戻す際には返還されます。 ⑥火災保険・家財保険 賃貸物件に入居する際と同様、リースバックの際も賃借人としての火災保険・家財保険に加入する必要があります。大家や保険会社によって金額は異なりますが、2年で2万円程度の場合が多いです。 かかる諸費用としては上記のようなものがあります。 これらは購入する業者や投資家によっても変わってくるもので、場合によってはこの他にも費用が発生する場合もあるでしょう。 ここで重要なのはいくら諸費用が安いからと言って安易に契約を進めるのではなく、諸費用がかかったとしても家を高い金額で買ってくれて、なおかつ月々の家賃が安い場合、そちらの方が最終的にはお客様にとっては良い条件となり得ますし、諸費用は安いが2年間で退去が必要となる場合もありますので、注意深く見極める必要があります。 家スクのリースバックでは多くの業者や投資家の金額や諸条件を比較し、お客様にとって ベストなリースバックを実現させます。 ぜひ気軽にご相談ください。
ブログ
-
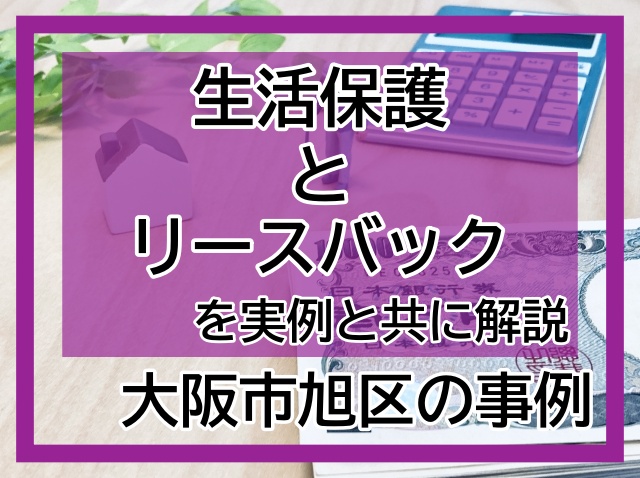
「生活保護とリースバック」を実例と共に解説 ~大阪市旭区の事例~
今回ご相談いただいたのは、大阪市旭区に住む50代の男性からです。 生活保護を受給しているが、リースバックは可能ですか? というお電話を最初にいただいたので、ご自宅に訪問し詳しくお話をお伺いしました。 詳しいご相談内容としては、現在自宅にご相談者様とお母様の二人暮らしで、これまでは料理人として腕を振るってきたが、数年前から糖尿病による歩行障害が理由でお仕事ができない状態になってしまわれたそうです。 現在、ご相談者様は生活保護を受給し、お母様は僅かな年金でなんとか暮らしている状態でした。 ご自宅は7年前に亡くなったお父様の名義のままで、相続登記はされておられませんでした。 生活をする上でだんだんと膨らんでしまったカードローン等の借入が約300万円あり、返済が滞っているため、カード会社から訴訟の通知が届き始めてしまったとのことです。 当然このまま放っておくわけにはいかないのですが、かといって返済するお金もありません。 お父様名義のままになっているご自宅を売却し、借入の返済に充てることを考えたそうですが、高齢のお母様もおられるので引越しは躊躇われるし、引越しをする資金もないのでリースバックを希望している。 というのが、大まかなご相談内容です。 実際にどのように進めていったのかを解説していきます。 ・親の家とはいえ、自宅があるのに生活保護は受給できるの? 相談内容の中で、ご相談者様は生活保護を受給しているが、亡くなっているとはいえ親の所有する家にお住まいです。 そもそもそのようなことが可能なのかと疑問に思われた方もいるかもしれません。 結論から言うと、親名義の家に生活保護を受給しながら住み続けることは可能です。 賃貸の物件に住みながら生活保護を受給している場合、毎月の生活保護費に家賃分が住宅扶助として加算されます。 もちろん、住宅扶助の部分はいくらでも加算されるわけではなく、市町村によっても異なりますが、おおよそ4万円を上限に毎月の家賃分が加算されます。 しかし、賃貸の物件ではなく親名義の家の場合、当然家賃は発生しないので住宅扶助は加算されることはありません。 そして、親が亡くなって家を相続したとしても、相続した家の資産価値が高い場合は売却し、その売却で得た資金で生活を送ることを求められる為、生活保護を受給したまま家を保有し続けることは認められませんが、資産価値が低いと役所が判断した場合、売却したとしてもすぐにその売却資金が尽きてしまい、また生活保護を受給する必要が出てきます。 しかもその際には家を売却しているので、住宅扶助も加算する必要が出てくる可能性が高いため、それならば資産価値の低い家の場合にはそのまま住み続け、住宅扶助を支給しないという判断に至るケースがあるのです。 今回はまさしくそのケースに当てはまっていたので生活保護を受給しながらお父様名義の家に住み続けることが出来ていたのです。 ・生活保護を受給したままリースバックを利用する 今回のケースではカードローンの借入が約300万円あるのでこれをどうするのかがネックとなります。 そこでまず家の査定を行いました。 大阪市旭区の築50年ほどの木造の家で、建物の価値はほぼゼロです。 土地は70㎡程の土地なのですが、前面道路が建築基準法上の道路ではないため、原則として将来建物を再建築することができない土地でしたので、市場価値としては非常に低いと判断されます。 査定結果としては売買代金350万円、家賃40,000円/月という結果です。 通常のリースバックの場合、この条件をお客様が承諾していただければ、そのまま契約し、売買代金でカードローンを全額返済し、毎月家賃を支払いながら住み続けるという流れで進められるのですが、今回は生活保護が絡んでいるため、すぐに進めることはできません。 家を売却するのであれば、その売却金額が本当に妥当なのかを役所にも承諾してもらう必要があるのです。 家を売却し、借入を返済したとしてもまだ資金が手元に残る場合、当然に生活保護は打ち切られてしまいます。 今回は350万円という査定金額の為、ここから300万円を返済し、相続登記も未了のため、その費用も司法書士に見積もりを作成していただき算出します。 その他にも細かい諸費用や、カードローンの借入も利息や遅延損害金等で300万円より膨らんでいたため350万円で売却した場合、最終的に手元には資金は全く残りません。 役所に当社の査定書を提出し、350万円という金額の妥当性の判断を仰ぎました。 2週間ほどで返答があり、承諾していただくことができました。 結果として売却後もリースバックでそのまま住み続けられ、住宅扶助も支給されるので、今回は相談者様の希望が無事に叶う形となりました。 ・まとめ このように、生活保護とリースバックは役所の承諾が得られれば組み合わせて利用することが出来ます。 住み慣れた家にそのまま住み続けられますので、生活保護を受給している方や、今後生活保護を受給することを検討しており、家もある場合は当社にご相談いただければ、ご相談者様の状況を慎重に見極め、役所とも連絡を取り合いながらなるべく希望に添えるよう進めさせていただきます。 ・リースバックの流れの図 株式会社家スクでは大阪・和歌山・奈良・兵庫において多くのリースバックの実績があります。 ・家スクのリースバック、7つの特徴 相談は無料です。 お気軽にお問合せ下さい
ブログ

 0120-778-078
0120-778-078





