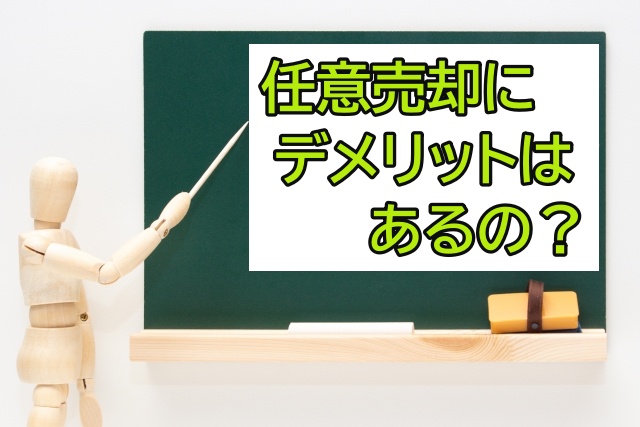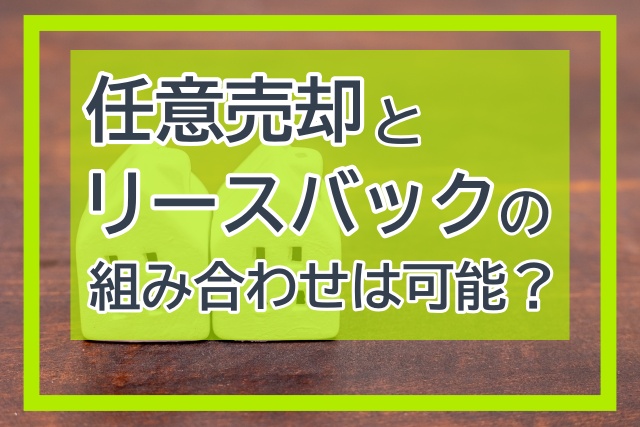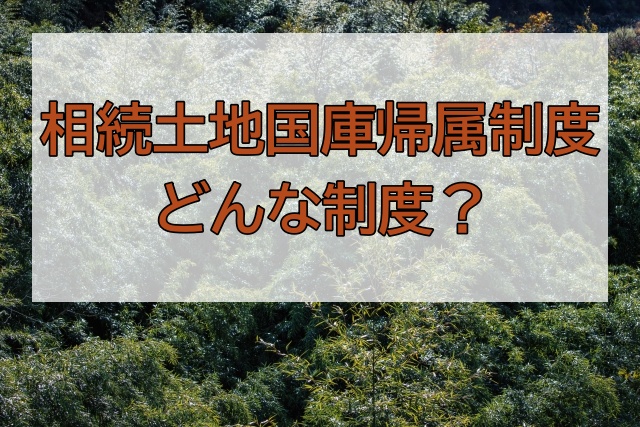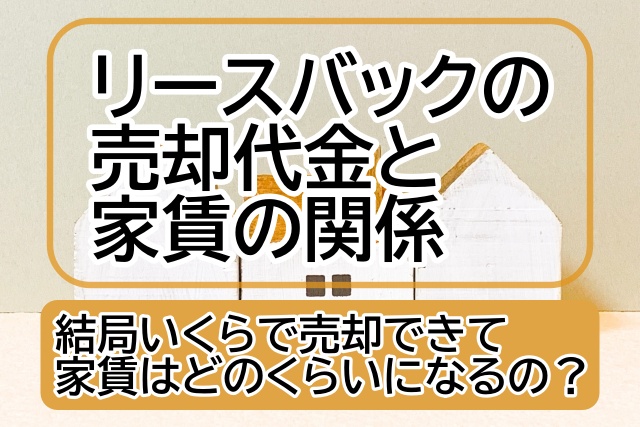blog
離婚したら住宅ローンの連帯保証人から外れられるの?
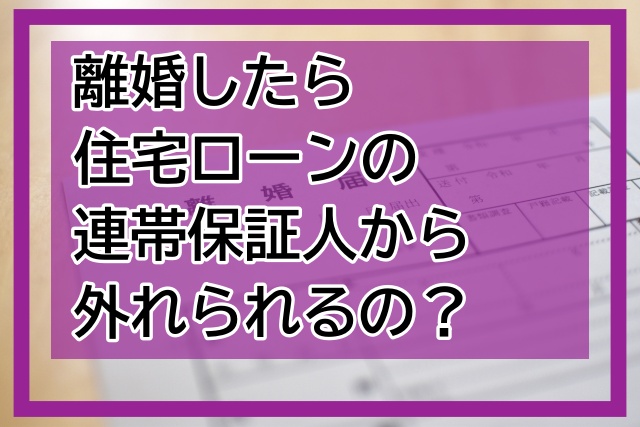
- ブログ
- ブログ
任意売却の相談をお受けする中で離婚が絡むケースは非常に多く、その中でもよく聞かれる質問が「離婚をしたら、連帯保証人から外れることはできるのか?」というものです。
よくあるケースとしては、離婚をする上で奥様とお子様が家から引越しをするので奥様がなっている連帯保証人から外れたいというものです。
もちろん、その逆のパターンもあるでしょう。
こういった場合、連帯保証人から外れることは可能なのでしょうか?
結論から申し上げると、連帯保証人から外れるのは非常に困難です。
では、どういった理由で困難なのか、このような場合どうするのが良いのか。
今回は離婚に伴う連帯保証人について解説します。
・そもそも、連帯保証人とは?
主債務者(契約者本人)がローンの返済ができなくなった際に、代わりに返済するという契約を金融機関と交わした方、これが保証人です。
そして、連帯保証人は法律上、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」を持たない保証人のことを指します。
「催告の抗弁権」とは、債権者が保証人に支払うよう請求した際に、保証人は自分よりまず主債務者本人に請求するよう主張できる権利です。
しかし、連帯保証人は「催告の抗弁権」を持たないので、主債務者より先に支払うよう請求されたとしても、拒否することができません。
「検索の抗弁権」とは、債権者が保証人に対して支払いを求めた際に、自分よりも先に主債務者本人の財産をまずは差し押さえるよう主張できる権利のことです。
しかし、連帯保証人は主債務者より先に自身の資産が債権者に差押えられたとしても、それを拒むことはできないのです。
「分別の利益」とは、主債務者に代わって複数の保証人が存在する場合、それぞれの保証人は、その人数で割った分だけの金額を支払えばよいとされる権利です。
例えば、AとBの2人の保証人がいる場合、Aは自分の負担分だけを支払えばよく、Bが支払わなかったとしてもAには関係ないのです。
しかし、連帯保証人に分別の利益はないので、主債務者と同様に全額を支払う義務があります。
仮に連帯保証人が何人いたとしても、それぞれが借金の全額を返済する義務を負うのです。
このように保証人とは違い、連帯保証人は3つの権利がないことで主債務者本人と同様の返済義務を負うことになり、いわば主債務者と運命共同体とでも言えるでしょう。
・どうして連帯保証人から外れられないのか
まず、連帯保証人になるという契約は主債務者と間で交わしているものではなく、銀行との間で交わしているものという認識が必要となります。
住宅ローンの連帯保証契約は、主たる債務者が住宅ローンを払えなくなった際に、連帯してその債務を支払う義務を負う契約です。
この契約は、あくまでもローンを貸す「銀行」と「連帯保証人」との契約であり、主たる債務者との契約ではありません。
つまり、離婚をするからと言っても銀行にしてみれば関係のない話で、連帯保証契約はそのまま有効であり続けるのです。
主債務者が払えなくなった際に代わりに支払ってくれる連帯保証人を無条件で外すというのは銀行にとってみれば何のメリットもないので、無条件で連帯保証人から外れるということはあり得ないのです。
唯一、連帯保証人から外れられる方法があるとすれば、代わりに連帯保証人になってくれる方を見つけるというものがあります。
しかし、この方法は現実的ではありません。
なぜなら、そもそも自分が住むわけでもない家の無関係な住宅ローンの連帯保証人になる方が見つかることがほとんどないからです。
また、仮に見つかったとしても銀行の承諾が当然必要になります。
連帯保証人となり得る収入や返済能力の審査があり、銀行が承諾すれば代わりに連帯保証人となってもらえますが、かなりハードルは高いでしょう。
・離婚後に主債務者が住宅ローンを払えなくなったら
もし、離婚後に主債務者が住宅ローンを払わなくなってしまうと、当然ながら連帯保証人に請求が来てしまいます。
前述の通り、離婚していても銀行には関係なく連帯保証人である限り請求を免れることはできません。
そしてそのまま支払えずにいた場合どうなるのでしょうか。
・個人信用情報に傷が付く(ブラックになる)
主債務者が返済できず、連帯保証人に請求が来た場合は当然返済義務がありますが、もし返済ができなかった場合は主債務者と共に、連帯保証人も個人信用情報に傷が付いてしまします。そのローンの支払いができないと返済遅延で前のご主人と一緒に信用情報に傷が入ります。(いわゆるブラックリストに載る、という状態です)
・家が競売で強制的に安価で売られてしまい、多くの残債が残る
主債務者、連帯保証人ともにローンの返済をしないままにすると、最終的に金融機関は裁判所に競売の申し立てをし、競売の手続きが開始されてしまいます。
引越しする家が売られるのであれば問題はないかと考えがちですが、競売には多くのリスクが潜んでいます。
競売は基本的に実際の市場価格の6~7割程度で売られることが多いため、競売の後も住宅ローンが残ってしまう可能性があるのです。
住宅ローンが残ってしまうと、当然金融機関からは主債務者と共に連帯保証人にも支払うよう督促してきます。
しかも、原則残ったローンを一括で支払うよう督促してくるのです。
給料や資産が差し押さえられる可能性も
競売になった後、住宅ローンがそれでも残ってしまった場合、残債は一括で返済するように主債務者と連帯保証人に対して請求が来ますが、一括で払えるはずなどありません。
そのまま支払えずにいると、最悪の場合給料の差押や資産がある場合はその資産が差し押さえられる可能性もあります。
このように、離婚と共に引越しをするから自身には関係ないと思っていても、連帯保証人になっている限り返済義務からは逃れられません。
きちんと離婚をする段階で話し合って対策を立てておく必要があります。
・離婚時に連帯保証人になっている場合の対策
離婚をする際に連帯保証人になっている場合、そのままの状態で仮に引越しをし、主債務者と連絡すら付かなくなってしまうと、突然金融機関から督促の通知が届くことすらあり得ます。
また主債務者と連絡も取れなければ手の打ちようがありません。
そうはならないためにも、離婚をする段階できっちりと対策をしておく必要があります。
・住宅ローンの返済条件を公正証書にする
離婚時に口約束で「住宅ローンは今後どっちが支払う」といったことを決めているご夫婦がありますが、これはトラブルの元です。
この条件をきっちりと公正証書にしておけば、将来約束が守られなかった場合に相手の資産等をすぐに差し押さえることが出来るのです。
例えば、離婚後は家に住み続ける夫が住宅ローンも返済するという内容の公正証書を作成しておけば、将来、約束が守られずに金融機関から督促等が届いた際に、夫の給料や資産を差し押さえることが出来るようになるのです。
ただし、差し押さえようと思っても差し押さえる資産がなければなんの意味もありません。
結局金融機関は主債務者、連帯保証人の双方に支払うよう督促し、その後競売をすることになるのです。
・住宅ローンの借換えを検討する
例えば主債務者が夫、連帯保証人が妻の場合、離婚をする際に住宅ローンの借換えを行い、夫の単独での借り入れにしてしまうということが出来るなら、将来のトラブルにはなりません。
しかし、この方法も新たに借り入れをする銀行の審査が必要となり、なかなかハードルは高い方法と言えるでしょう。
・家を売却する
離婚時は、せっかく購入した家なのでどちらかがそのまま家に住み続ける、という選択を取ることが多いですが、共有名義であったり、今回解説しているような連帯保証人になっていたりした場合、かなりの確率で将来トラブルになります。
そもそもどちらかが出ていった後、一人で住むには家が広すぎるということもありますし、今まで夫婦で協力して返済していた住宅ローンを突然一人で返済していくとなっても、どこかで躓いてしまう方が非常に多いのです。
そうなる前に離婚をするタイミングで売却をするというのが将来トラブルにならないためにも一番良いのではないでしょうか。
売却をして住宅ローンが全額返済できればそれでいいですし、手元に残った資金は財産分与の対象となり夫婦で話し合って分けることになるでしょう。
もし、売却しても全額返済できない場合は「任意売却」を検討する必要があります。
まとめ
離婚はそれだけでもかなりの時間と労力を要します。
そこに住宅ローンの問題も重なってくるとどうすれば良いのか分からなくなってしまう方も多いはずです。
しかし、そのままにしておくと後になって取り返しのつかないトラブルにも発展しかねません。
離婚と連帯保証人の問題は必ず専門家に相談しながらどのように進めるのが最善なのかを慎重に見極める必要があります。
当社では離婚や連帯保証人の問題も含め多くのトラブルを抱えた方の相談を解決してきました。
弁護士や司法書士等の士業の方とも連携しており、ワンストップで相談が可能です。
大阪、和歌山、奈良、兵庫で離婚や連帯保証人の問題でお悩みなら当社までご相談ください。きっと力になれるはずです。

 0120-778-078
0120-778-078